- スタッフブログ
- ホーム
歯列矯正の医療費控除に必要な書類まとめ|レシート・診断書・明細書は?
歯列矯正には高額な費用がかかるため、「少しでも節税できないか」とお考えになる患者さまも多いのではないでしょうか。そんなときに活用したいのが「医療費控除」です。医療費控除を正しく受けるためには、所定の書類をそろえて申告する必要がありますが、「何を残しておけばいいの?」「診断書は必要なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるはずです。
そこで本コラムでは、歯列矯正で医療費控除を受ける際に必要な書類について、具体的にわかりやすく解説いたします。申請時に慌てないためにも、しっかり準備しておきましょう。
▼歯列矯正の医療費控除で必要な書類
はじめに、歯列矯正の医療費控除における領収書・レシートの取扱いと申請の際に必要となる書類を確認していきましょう。
◎領収書とレシートの取扱い
医療費控除の申告において最も重要なのが「領収書」です。歯科医院での治療費を支払った証明として、確定申告時に控除額の根拠となります。歯列矯正の領収書には、治療を受けた日付、医療機関名、治療内容、支払金額などが明記されている必要があります。年間を通じて分割で支払うことが多いため、すべての領収書をきちんと保管しておくことが大切です。
一方、「レシート」は一般的には医療費控除の書類としての正式な効力は弱いとされています。歯科医院によっては、領収書ではなくレシート形式の明細を発行することもありますが、確定申告では領収書の提出または保管が基本です。どうしても領収書を紛失した場合には、医院に再発行を依頼するか、レシートに治療内容と医療機関名が記載されていれば代用可能なケースもあります。いずれにせよ、記載情報に不備がないかを確認し、必要に応じて補足資料を用意しておきましょう。
◎医療費控除の明細書
確定申告で医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の提出が必要です。この書類には、患者さまごとの医療機関名、支払年月日、支払金額、補填金額(保険や給付金など)を記載します。
明細書の作成には、1年間に支払った歯列矯正の費用を正確にまとめておく必要があります。分割で支払っている場合には、申告対象年に実際に支払った金額だけを記載するよう注意しましょう。
この様式は、国税庁の公式ホームページからダウンロードでき、PDFまたはExcelでの作成が可能です。また、e-Taxを利用する場合は、自動入力の機能やマイナポータル連携を活用すると便利です。明細書の記入に不安がある場合は、事前に税務署に相談しておくと安心です。
◎医療費通知書
「医療費通知書」とは、健康保険組合や協会けんぽから送られてくる年間の医療費の通知書です。通常、確定申告の時期である1月〜2月に手元に届きます。
この通知書には、保険診療で受けた医療費や薬局での支払内容などが記載されており、医療費控除の明細書の代替資料として使用することができます。ただし、歯列矯正の多くは自由診療(自費治療)に該当するため、医療費通知書には金額が反映されないことがほとんどです。
そのため、歯列矯正の費用を控除対象に含める場合は、必ず領収書を基に明細書を別途作成する必要があります。通知書を補助資料として活用する形で保管しておきましょう。
◎確定申告書
医療費控除を実際に受けるには、最終的に「確定申告書」を提出する必要があります。確定申告書には、控除額を反映させた所得金額や税額などを正確に記載しなければなりません。
確定申告書は税務署でもらうこともできますし、国税庁のホームページやe-Taxを利用すれば自宅から作成・提出することも可能です。e-Taxを使えば、明細書や収支の自動計算が行えるため、医療費控除を受ける際のミスも防ぎやすくなります。
歯列矯正にかかる費用が高額であっても、適切な手順で確定申告をすれば還付が受けられるケースも多いため、必要書類と手順を事前にしっかり確認しておきましょう。
▼診断書は基本的に必要ない
一般的に、歯列矯正の医療費控除を申請する際に、診断書の提出は原則として求められていません。確定申告では「医療費控除の明細書」と「領収書」の保存(または提示)が基本であり、診断書がなくても申請自体は可能です。
とくに、治療が明らかに医療目的であると判断できるケース(例:お子さまの噛み合わせ不全や顎の発育不全に対する矯正など)では、追加資料を求められることは少ないのが実情です。
◎稀に診断書が求められるケースも
ただし、以下のようなケースでは診断書の提出が求められる場合があります。
・審美目的との区別があいまいな成人矯正
・金額が極端に高額で、治療の必要性が不明瞭な場合
・税務署からの照会を受けた場合
そのため、心配な場合はあらかじめ歯科医院に診断書の作成を依頼しておくと安心です。診断書には「咀嚼機能の改善のための矯正治療であること」など、医学的な必要性を記載してもらいましょう。
▼医療費控除の明細書の書き方
医療費控除の申告には、「医療費控除の明細書」が必要です。この書類は以下のいずれかの方法で入手できます。
・国税庁のホームページからダウンロード(PDFまたはExcel形式)
・税務署の窓口で配布
・e-Taxソフトにて自動作成
また、マイナポータルと連携することで、医療費の一部を自動的に入力する機能もあります。より簡単に作成したい方には、e-Taxの活用がおすすめです。
◎明細書の書き方
明細書には、以下の情報を正確に記載します。
・治療を受けた方の氏名(患者さまごと)
・医療機関名(歯科医院名)
・支払金額
・保険金などで補てんされた金額(なければ0円)
歯列矯正費用を記載する際には、年内に支払った金額のみを記入してください。分割払いで来年以降の支払いがある場合でも、その年に実際に支払った分だけが控除対象となります。
また、1年間の医療費が合算で10万円を超えない場合や、課税所得が少ない場合には控除額が発生しないケースもありますので注意が必要です。
◎迷ったら税務署へ相談を
明細書の記載内容や添付資料について不安がある場合は、無理に自己判断せず、最寄りの税務署に相談しましょう。担当者が丁寧に対応してくれます。
歯列矯正の医療費控除は、正しく準備すれば申請しやすい制度です。書類の不備によるトラブルを防ぐためにも、事前に確認をしておくことが大切です。
▼まとめ
歯列矯正の医療費控除を受けるには、領収書や明細書を中心とした必要書類を正しくそろえておくことが大切です。診断書は基本的には不要ですが、審美目的との判断がつきにくい場合には準備しておくと安心です。明細書の書き方で迷った際は、遠慮なく税務署に相談しましょう。矯正治療は高額になりやすいため、制度を活用して少しでも負担を軽減していくことが大切です。お子さまの治療やご自身の歯並び改善のためにも、申告の準備は早めに行いましょう。
Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by
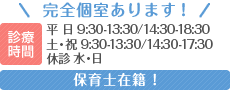
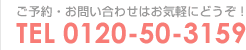
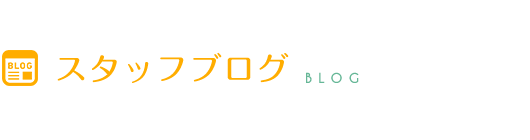
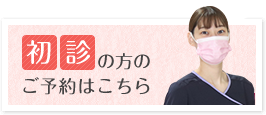
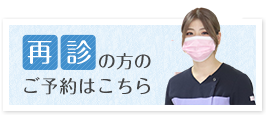


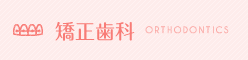

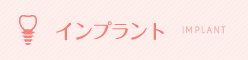
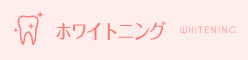
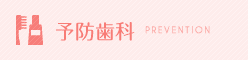

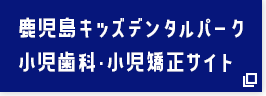
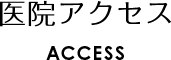
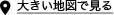
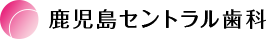
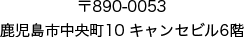
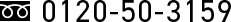
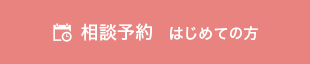
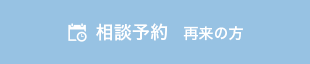
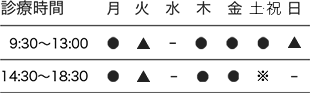
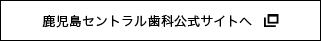
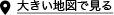
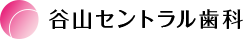
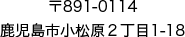
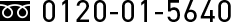
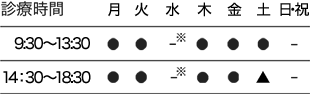
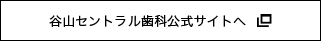
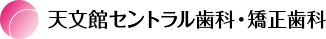
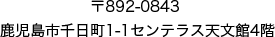
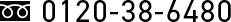
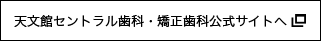
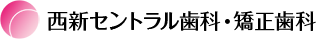
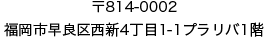
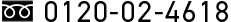
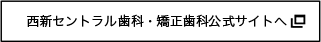
2025年5月2日 (金)
カテゴリー: 矯正歯科