- スタッフブログ
- ホーム
歯列矯正の医療費控除のやり方を徹底解説|申請手順から注意点まで
歯並びを整える歯列矯正は、見た目の改善だけでなく、虫歯や歯周病の予防、噛み合わせによる顎関節の負担軽減など、医療的な効果も期待できる治療です。しかし、決して安いとは言えない費用に悩む患者さまも多くいらっしゃいます。そこで知っておきたいのが「医療費控除」です。
実は、条件を満たせば歯列矯正でも医療費控除の対象となり、確定申告を通じて税金の一部が還付される可能性があります。本記事では、歯列矯正の医療費控除のやり方を中心に、申請の流れや注意点、困ったときの対処法まで、分かりやすく解説していきます。
▼歯列矯正の医療費控除のやり方
-
医療費控除の対象となるか確認する
まずは、歯列矯正が医療費控除の対象となるか確認しましょう。対象になるのは、「治療を目的とした矯正」に限られます。たとえば、お子さまの噛み合わせや発育に影響する歯並びの改善、発音障害や顎関節の異常による矯正は医療費控除の対象となります。一方、審美目的の矯正は原則として対象外です。成人の方でも、噛み合わせによる機能的な問題を矯正する場合は、医療費控除の対象になり得ます。
-
必要書類を準備する
医療費控除の申請には、以下の書類が必要になります。
◎医療費控除の明細書
確定申告書に添付する書類で、1年間に支払った医療費をまとめたものです。令和5年分以降は、領収書の提出は不要ですが、自宅で5年間の保管が義務付けられています。
◎医療費通知
健康保険組合から届く医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付することで、明細の一部を簡略化できます。ただし、歯列矯正は自費診療のため、記載されていないケースが多いです。
◎領収書・レシート
提出は不要ですが、支払い内容を証明できるよう保管しておきましょう。
◎診断書(求められた場合のみ)
通常、歯列矯正の医療費控除では診断書の提出は不要ですが、税務署から求められることがあります。その際は、歯科医院に依頼して発行してもらいましょう。
-
確定申告書を作成する
次に、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」や税務署窓口、またはe-Taxを利用して確定申告書を作成します。医療費控除の明細を入力し、必要に応じて添付資料を用意します。
-
確定申告を提出する
確定申告の提出期間は、原則として毎年2月16日〜3月15日です。e-Taxを利用するか、税務署に持参・郵送で提出します。申告後、還付金がある場合は、指定の銀行口座に振り込まれます。
▼歯列矯正の医療費控除で注意すべき点
次に、歯列矯正で医療費控除を利用する際に注意すべき点を解説します。
◎審美目的の矯正は対象外
歯列矯正には「治療目的」と「審美目的」の2つがありますが、医療費控除の対象となるのは治療を目的とした矯正治療に限られます。「歯並びを整えて見た目を美しくしたい」「口元の印象をよくしたい」といった審美目的の矯正は、たとえ高額な費用がかかった場合でも控除の対象外となる点に注意が必要です。
一方で、お子さまの発育に影響を及ぼす噛み合わせや、顎関節への負担、発音障害の改善など、医学的な理由に基づいた矯正治療であれば、年齢にかかわらず医療費控除が適用される可能性があります。成人矯正でも、咬合異常や顎関節症などの症状があれば控除対象と判断されるケースもあります。
申告時に治療目的であることを証明するために、必要に応じて歯科医院で診断書の発行を依頼しておくと安心です。特に成人矯正の場合は、治療の必要性を明確に示す書面が求められることがあるため、事前に歯科医師と相談しておくとよいでしょう。
◎医療費控除の対象期間に注意
医療費控除では、「費用を支払った日」が基準になります。契約日や治療開始日ではなく、実際に費用を支払った年の確定申告で申請を行う必要があります。この点を誤解している患者さまも多く、注意が必要です。
たとえば、2024年12月に歯列矯正の契約を行い、実際の支払いが2025年1月に行われた場合、その費用は2025年分の医療費控除として、2026年2月〜3月にかけて行う確定申告で申請することになります。契約日が早くても、支払日が翌年であれば、その年の分として計上されるのです。
また、治療費を複数年にわたって分割で支払う場合には、各年に支払った金額だけがその年の控除対象になります。一括払いではない場合、1年分ごとに支払記録を管理しておくことが、正しい申告に繋がります。
◎家族分の合算が可能
医療費控除は、患者さまご本人だけでなく、「生計を一にする家族」の分も合算して申請できます。これは、同じ家計で生活している家族の医療費を1人分にまとめて控除申請できる制度で、申請額を増やすことで還付金額が多くなる可能性があります。
たとえば、お子さまの歯列矯正治療費を親御さまが支払っている場合、その金額は親の医療費控除として申請できます。これは、親が子供の生活費を負担しており、生計を一にしているとみなされるためです。
この制度を活用するには、家族全員分の医療費領収書や支払記録を1年分まとめて整理しておくことが重要です。税務署へ提出する「医療費控除の明細書」には、家族ごとの名前と支払額を記載する欄がありますが、合計でまとめることも可能です。
▼まとめ
歯列矯正の医療費控除は、条件を満たせば高額な治療費の一部が還付される大切な制度です。治療目的であれば、お子さまはもちろん、大人の矯正でも対象となる可能性があります。医療費控除のやり方にはいくつかのステップがありますが、明細書の記入や領収書の保管など、基本を押さえておけば難しくありません。もし不明点があれば、税務署への相談も視野に入れ、安心して申請手続きを行ってください。
Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by
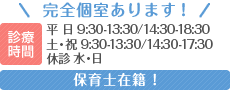
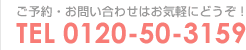
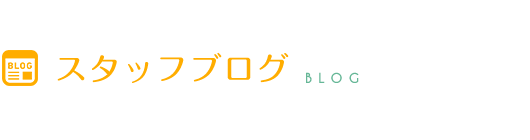
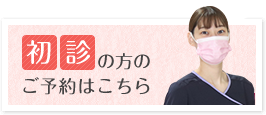
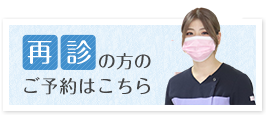


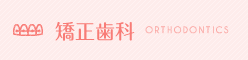

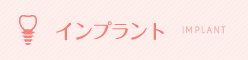
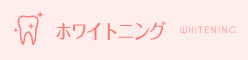
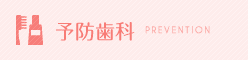

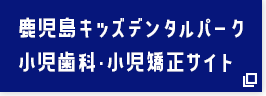
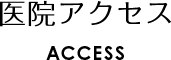
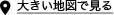
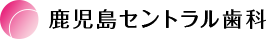
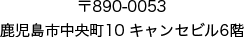
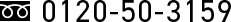
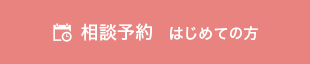
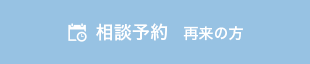
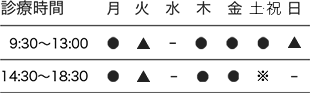
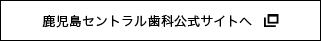
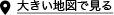
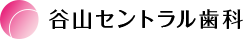
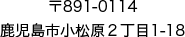
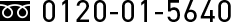
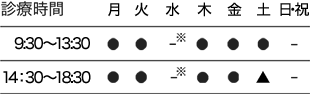
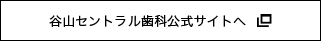
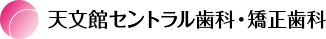
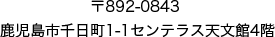
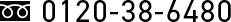
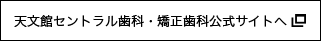
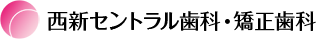
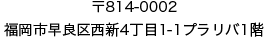
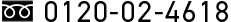
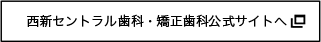
2025年5月2日 (金)
カテゴリー: 矯正歯科