- スタッフブログ
- ホーム
契約前にここを確認!矯正歯科で絶対後悔しないための最終チェックポイント
皆さん、こんにちは。鹿児島セントラル歯科です。
「矯正を始めたあとに『こんなはずじゃなかった…』と感じてしまう」――そんな声を耳にするたび、私たちは胸が痛みます。矯正治療は時間も費用もかかる大きな選択ですから、契約前の“最終確認”こそが成功のカギを握ります。本コラムでは、契約書にサインをする前に必ず押さえておきたいチェックポイントと、矯正歯科で後悔しやすい人の共通点を解説します。これから治療を検討される患者さまや保護者の方にとって、矯正歯科選びの羅針盤となれば幸いです。
▼矯正歯科の契約前の最終確認(チェックポイント)
矯正歯科の契約前に歯、以下の6つのポイントをチェックしましょう。
1.治療計画とゴールの共有
◎現状分析
矯正治療を成功させるためには、まず現状の正確な把握が不可欠です。顔貌写真や頭部X線規格写真(セファログラム)、口腔内スキャナー、歯列模型などを用い、上下顎の歯列の位置関係や顎骨の成長バランス、咬合状態を多角的に評価します。特にCT(コンビームCT)では、歯の根の位置や顎骨の厚み、埋伏歯の有無なども立体的に把握でき、治療計画の精度が飛躍的に向上します。
◎ゴール設定
歯並びの美しさだけでなく、咬合の安定性や顎関節への負担の軽減など、機能面を含めたゴールを設定することが大切です。「出っ歯を治したい」「すきっ歯をなくしたい」といった希望だけでなく、「歯根の移動に制限がある部位」や「骨格性の不正咬合は外科手術が必要となる可能性」など、医学的な限界やリスクも含めて説明を受けましょう。事前に目指すゴールの明確な合意がなければ、治療の満足度は下がる傾向にあります。
2.費用内訳と追加料金の有無
◎総額提示
矯正歯科では、初回診断料、装置装着料、毎月の調整料、保定装置(リテーナー)、定期観察費用など、複数の費用項目が発生します。料金体系がパッケージ化されている場合でも、各費用が何に対応するかを明示してもらうことが重要です。特に保定装置の費用が別料金かどうかは、確認漏れが起きやすい部分です。
◎追加発生ケース
治療中に装置が破損したり、治療内容の見直し(再診断)が必要になったりした場合、追加料金が発生する可能性があります。また、治療途中で歯が動きにくい場合や、想定通りに改善が進まなかった場合などには、補助的な装置や延長治療が必要になることもあります。その際の対応と費用負担の有無については、契約書や説明書を通じて明確にしておくことが、矯正歯科 最終確認の中でも特に重要です。
3.治療期間と通院スケジュール
◎標準期間
歯の移動速度は、加齢や骨の代謝速度によって異なりますが、通常、全体矯正は18か月~36か月程度が目安です。特に骨の柔軟性が高い成長期の子供の場合、早期の介入によって治療期間が短縮されるケースもあります。一方、部分矯正や前歯部のみの改善であれば6か月〜1年程度で完了することもあります。
◎通院頻度
ワイヤー矯正では、歯の動きに合わせて月1回のペースでワイヤーの調整が必要です。マウスピース矯正では、6〜8週間ごとの経過観察が主流ですが、口腔内スキャナーを用いた遠隔モニタリングシステム(テレデンティストリー)を導入している場合には、来院回数が少なくなることもあります。患者さまのライフスタイルに応じて、通院の柔軟性があるかもチェックしておきましょう。
4.担当医とチーム体制の確認
◎専門資格と臨床経験
矯正歯科の治療は、顎骨や歯列、筋機能に対する包括的な知識と、長期にわたる治療経験が求められます。矯正専門医として信頼できるかどうかを判断するひとつの目安として、「日本矯正歯科学会認定医」や「臨床指導医」の資格が挙げられます。これらの資格は、一定の症例数・学会活動・知識更新が求められるものであり、継続的に専門性を維持している証です。また、症例写真や治療前後の資料を提示できるかどうかも重要な判断基準となります。患者さまの症状に近い症例を確認することで、治療イメージを明確にすることができます。
◎チーム医療の体制
矯正治療は、歯の移動だけで完結するものではありません。むしろ口腔内全体の健康状態が、矯正治療の成功に直結します。たとえば、歯周病のリスクが高い患者さまには歯科衛生士による定期的な歯周管理が必要ですし、親知らずの抜歯が必要なケースでは口腔外科医との連携が求められます。また、小児矯正では耳鼻科的な評価や小児科との連携が必要となる場合もあります。
5.使用する装置と治療選択肢
◎矯正装置の種類と特徴
矯正装置にはさまざまな種類があり、症状やライフスタイルに応じて適切な選択を行う必要があります。代表的な装置には以下のようなものがあります:
マルチブラケット装置(ワイヤー矯正):金属やセラミック製のブラケットを歯の表面に装着し、ワイヤーを通じて歯を動かします。適応範囲が広く、重度の不正咬合にも対応できます。
マウスピース型矯正装置:透明なアライナーを段階的に交換しながら歯を移動させます。審美性が高く、取り外し可能な点が特徴ですが、自己管理が求められます。
機能的矯正装置(お子さま向け):筋機能療法を併用しながら、顎の発育を正しい方向に導く装置(例:バイオネーター、FKOなど)。咬合誘導の一環として小児期から使用されます。
◎症例に応じた選択肢提示
矯正装置にはそれぞれ利点と限界があるため、患者さまの症状に適した選択肢を複数提示してくれるクリニックかどうかを見極めることが大切です。たとえば、骨格性の不正咬合(受け口や開咬)では、成長期の顎の成長を利用した早期治療や、成人であれば外科矯正が必要となることもあります。
単一の装置にこだわらず、症例に応じた最適な治療法を提案してくれる医療機関を選ぶことが、後悔しないための鍵です。
6.トラブル時の対応・保証体制
◎急患対応体制
矯正治療中は、装置の脱離・ワイヤーの刺さり・口内炎の発生・歯茎の腫れなど、緊急対応を要する場面が少なくありません。その際、対応可能な曜日・時間帯、連絡方法(電話・LINE・メールなど)や、臨時の処置ができる医師の体制が整っているかを事前に確認しておくことが重要です。特に、お子さまの治療中に痛みや違和感が起きた場合、迅速な対応ができるかどうかは保護者の方にとって安心材料となります。
◎保証とアフターケア
矯正治療終了後は、保定期間(リテーナー装着)を含めて、後戻りの防止が必要です。保定装置が破損した場合の再作製や、後戻りが起きた際の再治療に対する保証内容は契約前に確認しましょう。また、医院によっては保定期間中の経過観察を有料・無料で提供しているケースがあり、その取り決めも明確にしておくと安心です。
◎転居・転医の対応
治療途中で引っ越しなどの理由により通院が難しくなるケースも想定されます。その場合に紹介状の作成やデータの転送が可能かどうか、転院先との連携が取れるかも確認しておきましょう。特にマウスピース矯正の場合、治療データの共有体制が整っている医院であればスムーズな継続が可能です。
▼まとめ
矯正治療は“始める前の準備”が成否を分けます。治療計画・費用・期間・チーム体制・装置・保証という六つの観点で矯正歯科 最終確認を行い、疑問点はその場で解消しましょう。また、後悔しやすい方の特徴に自分が当てはまらないかを振り返り、正しい情報収集とセルフケアを徹底することが大切です。鹿児島セントラル歯科では、患者さま一人ひとりの価値観に寄り添い、安全で満足度の高い矯正治療をご提案しています。気になる点があれば、いつでもお気軽にご相談ください。
Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by
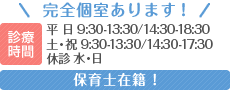
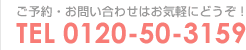
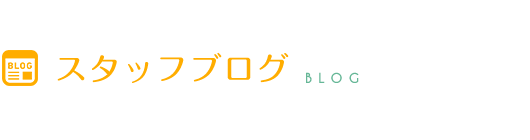
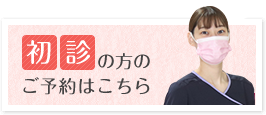
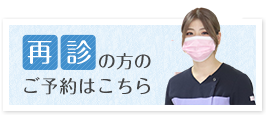


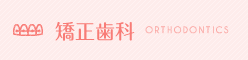

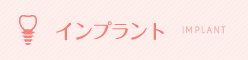
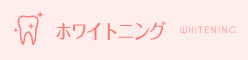
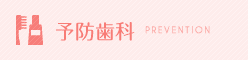

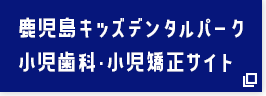
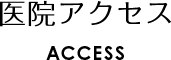
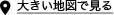
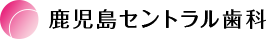
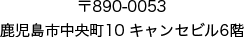
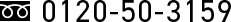
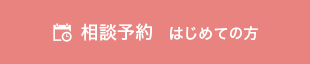
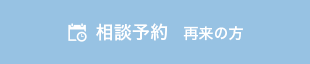
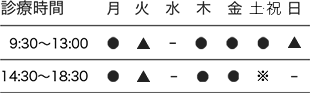
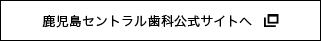
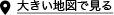
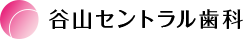
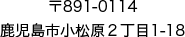
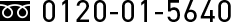
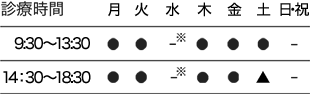
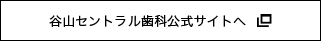
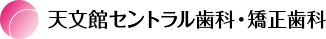
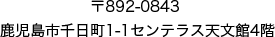
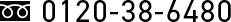
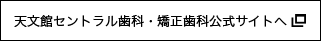
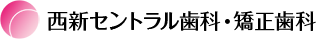
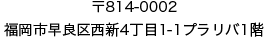
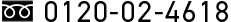
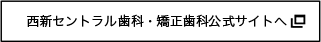
2025年7月10日 (木)
カテゴリー: 矯正歯科