- スタッフブログ
- ホーム
子供の歯並び、どうする?小児矯正歯科の選び方と開始時期
皆さん、こんにちは。鹿児島セントラル歯科です。
「子供の歯並びが気になるけれど、いつから矯正を考えるべき?」「どんな歯科医院を選べばいいの?」と迷われている保護者の方は少なくありません。近年では、お子さまの将来の健康や見た目に対する関心が高まる中、小児矯正を検討される方が増えてきています。
本コラムでは、小児矯正を始める最適なタイミングや、信頼できる矯正歯科の選び方を医学的な観点からわかりやすく解説いたします。
▼子供の矯正歯科の選び方
子供の矯正歯科を選ぶ際には、以下の5つのポイントに着目してください。
◎小児矯正に詳しい歯科医師がいるか
まず注目すべきは、小児矯正を専門的に扱う歯科医師が在籍しているかどうかです。子供の矯正は大人と異なり、顎の成長や永久歯の生え変わりを見越した計画が求められます。
専門的な知識と経験を持つ歯科医師であれば、成長発育に合わせた柔軟な治療が可能です。矯正歯科学会の認定医や、豊富な小児症例を扱っている実績があるかを確認するとよいでしょう。
◎一般歯科と連携しているか
矯正中は虫歯や歯茎のトラブルが起こりやすくなります。矯正専門医院ではなく、一般歯科と連携している、または一体型の歯科医院であれば、虫歯の予防処置や治療も同時に受けることができ、お子さまの口腔環境をトータルで管理できます。矯正歯科選びでは、矯正だけでなく日常の口腔管理にも対応しているかを見ておきましょう。
◎定期的な経過観察を丁寧に行ってくれるか
子供の矯正は、1期治療(乳歯〜混合歯列期)から始まるケースが多く、長期にわたる経過観察が重要です。装置をつける前後にかかわらず、定期的な診察で成長や歯並びの変化を見守ってくれる体制が整っているかを確認しましょう。「いつ矯正が必要になるか分からないけれど、とりあえず見ておいてもらいたい」というご相談にも柔軟に対応できる歯科医院は安心です。
◎装置や治療法に選択肢があるか
小児矯正の装置には、床矯正、拡大装置、マウスピース型装置など多様な種類があります。歯並びの状態やお子さまの性格、ライフスタイルに合わせて装置を選べるかどうかも大切なポイントです。一つの方法を一方的にすすめるのではなく、複数の選択肢を説明してくれる歯科医院であれば、納得のいく治療方針を立てやすくなります。
◎子供が通いやすい環境であるか
お子さまが緊張せず通院できる環境かどうかも見逃せません。院内の雰囲気、スタッフの対応、待ち時間の過ごし方などが良好であれば、治療の継続もスムーズになります。
また、矯正治療は長期間にわたることが多いため、通いやすい立地であること、予約が取りやすいことも現実的な選択の基準になります。
▼子供の矯正歯科の特徴と開始時期
小児矯正は、顎骨の成長を利用して歯列や咬合(噛み合わせ)のバランスを整える「成長期にしかできない矯正治療」です。永久歯が生えそろってから矯正を行う大人の治療とは異なり、顎の幅や前後的な位置関係をコントロールできる点が特徴です。具体的には、上顎と下顎の骨格的な不調和や歯列弓(しれつきゅう:歯並びのアーチ)の狭さを改善し、将来の歯並びの悪化を予防することが目的です。このように、小児矯正は「歯を並べるための治療」ではなく、「歯が正しい位置に並ぶための環境づくり」を行う、いわば“土台作り”の治療といえます。
◎一般的な開始時期の目安
小児矯正の開始時期として一般的なのは、混合歯列期と呼ばれる6〜9歳頃です。この時期は、前歯の永久歯(中切歯・側切歯)が生え始めると同時に、乳歯が順次脱落し、永久歯列へと移行する重要な発育段階にあたります。また、上顎の側方成長(横方向の拡大)は10歳前後でピークを迎えるとされており、それまでに適切な処置を行うことで、歯が正しい位置に並ぶためのスペースを確保しやすくなります。たとえば、以下のような所見が見られる場合には、矯正歯科への相談を早めに行うことが望ましいです。
・上下の前歯が正しく噛み合っていない(開咬、過蓋咬合、反対咬合など)
・永久歯が斜めに生えてきている、または重なり始めている
・顎が左右どちらかにずれている
・発音が明瞭でない、滑舌が悪い
これらは歯列の問題だけでなく、顎関節や咀嚼筋(そしゃくきん)のバランスにも影響を及ぼす可能性があるため、早期の評価が重要です。
◎もっと早く相談してもよいケース
6歳未満のお子さまでも、口腔機能や生活習慣に関連した異常が見られる場合には、矯正歯科の評価を受けておくことをおすすめします。
たとえば、以下のような症状は、将来的な不正咬合のリスク因子とされています。
・口呼吸が慢性的に続いている
・指しゃぶりや舌の突出癖(舌癖)が長期間続いている
・うまく噛めず、常に左右どちらかで噛む癖がある
・咀嚼や嚥下の際に口が開いてしまう
・発語が不明瞭で、サ行・タ行がうまく発音できない
これらの癖や口腔機能の問題は、顎の発育や歯の萌出方向に悪影響を与える可能性があり、MFT(口腔筋機能療法)などのトレーニングによって早期に改善を図ることが有効です。たとえ矯正装置をすぐに装着する必要がなくても、将来の治療方針を検討するうえで、早めの評価は大きなメリットとなります。
◎2期治療との違いを理解しておこう
小児矯正は「1期治療」と「2期治療」に大別されます。1期治療は主に成長期(小学校低〜中学年)に行われ、顎の骨格の調整や、永久歯が正しく並ぶための環境作りを目的とします。それに対して2期治療は、永久歯がすべて生えそろった12歳前後以降に行われ、歯の一本一本を精密に動かして理想的な咬合をつくる治療です。ワイヤー矯正やマウスピース型矯正装置(例:インビザラインティーンなど)が用いられます。
1期治療の効果には個人差がありますが、適切なタイミングで開始すれば、2期治療の負担を軽減したり、場合によっては2期治療自体が不要になったりすることもあります。
特に、抜歯矯正を回避したいと考える保護者の方にとって、1期治療で顎の成長を正しく誘導することは、大きな意味を持つといえるでしょう。
▼まとめ
お子さまの歯並びに関心を持ったとき、どの矯正歯科を選ぶか、いつ始めるかは非常に重要な判断です。矯正歯科 子供向けの治療は、ただ歯を動かすのではなく、成長とともに正しい噛み合わせを育むためのサポートでもあります。矯正を始めるタイミングや治療の必要性は、お子さまによって異なります。気になる症状があれば、まずは矯正相談を受けてみてください。鹿児島セントラル歯科では、保護者の方にも丁寧にご説明し、納得いただける治療を心がけております。将来の健やかな口元のために、今からできることを一緒に考えていきましょう。
Copyright © KAGOSHIMA CENTRAL CLINIC All Rights Reserved. platform by
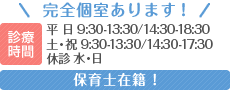
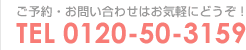
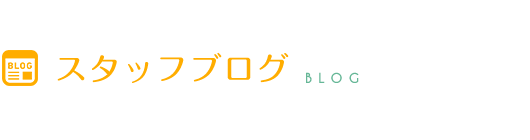
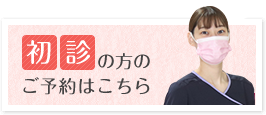
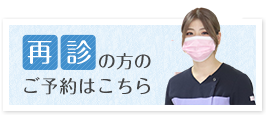


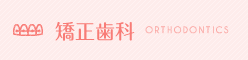

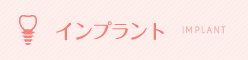
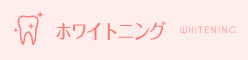
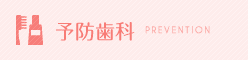

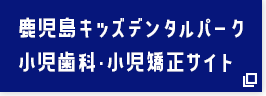
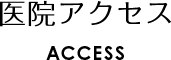
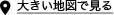
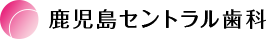
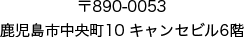
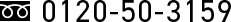
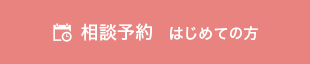
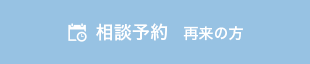
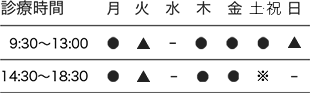
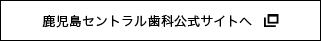
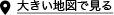
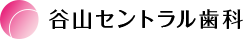
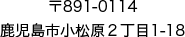
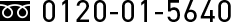
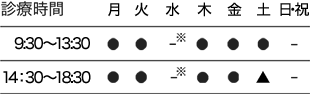
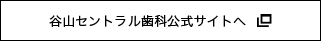
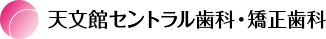
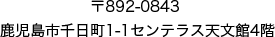
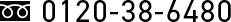
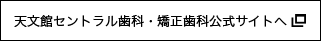
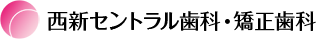
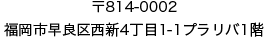
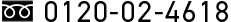
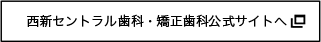
2025年7月14日 (月)
カテゴリー: 矯正歯科